6月2日(木)主催講座2「私たちの身近な野鳥との共生を考える~長きにわたる野鳥観察を通じて見えること~」の第3回「野外学習 石狩の野鳥を観察しよう」をはまなすの丘公園で行いました。講師は日本野鳥の会札幌支部長の猿子正彦さん、受講者は19名でした。
資料配布
・野鳥チェックリスト
・草原の野鳥を探そう
・石狩市民カレッジ講座 探鳥会のしおり 石狩浜と石狩灯台
・北海道ウォッチングガイド
・はまなすの丘公園 自然観察ガイドマップ
本年度初のバスツアー、新車での野外学習でした。天気予報に反して青空が顔を出し風もなく最高の野鳥観察日よりになりました。
受付時、事前レクチャーでは講師の猿子さんからは私は晴男の自己紹介から始まり、楽しい観察会の期待に皆笑顔で乗車しました。
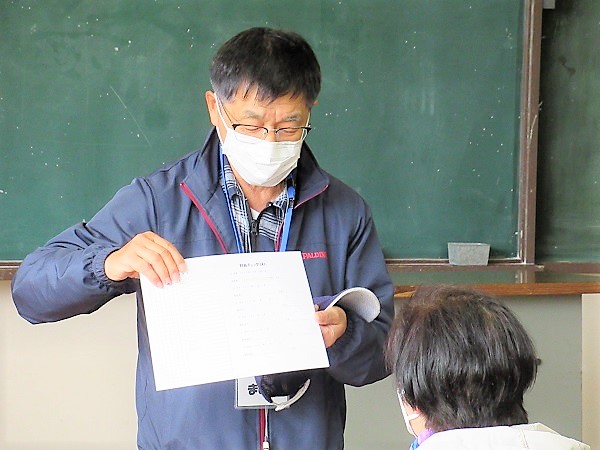
出発前、安全確認の徹底の申し合わせに基づき、シートベルトの確認、緊急時連絡先の記入確認を行いました。

ビジターセンターの駐車場に着いて、講師の猿子さんから今日の野鳥観察の注意事項について確認。
・私より先に出ないこと。
・鳥が人間を恐れる距離は10m、20mはOK。
・鳥は保護色が多いので目を凝らして見てください。その時大声は出さない。
・双眼鏡の扱い方について講習。ストラップの長さでベテランかどうか分かる。
双眼鏡での鳥の見方は見ている鳥に対して、頭と目線を固定して、目線の延長線内に双眼鏡を持ってくる。左右視度調整など意外と使い方を知らない人多く参考になりました。
〇講師は鳥に関しての知識は豊富で鳥を見つける早さに驚く。鳥が飛び込んでくるように見えるそうです。鳥の解説も幅広く聞いていても飽きることがありませんでした。
使っていた野鳥図鑑(山野の鳥・水辺の鳥)には鳴き声タッチペンで声を聞かせる仕組みもあったり、鳥の説明用紙芝居を用いて、参加者を楽しませる仕組みもあり、ガイドの参考にもなりました。


〇早速、駐車場で観察会が始まりました。次々と鳥たちが見られました。
・電線に止まっているカワラヒワ。
・ホオアカ~枝先に止まって鳴いているのはオスでその向いている先にはメスがいる。

・トビ~三味線に使うバチのような尾羽の真ん中が凹んでいて他の猛きんと判別できる。
・チゴハヤブサ~図鑑P49参照、今の時期は渡ってきたばかりで渡り疲れか、人が近づいても逃げないので観察しやすい。じっくり見られラッキーでした。

・5月から6月初めは渡りの季節で、長旅の疲れもあるのか、近づいてもあまり動かないので鳥見するには最高の季節。
・目立つ色なのがオス、メスは地味。メスは抱卵中も巣でじっとしているので目立たないような色彩になっている。
〇駐車場から堤防を超え石狩川側へ移動し東屋まで行くが丁度いい気温とそよ風が気持ちよい。ハマナスも目立つ大きな花を咲かせていた。

・ハシボソガラス~カラスにはハシボソガラスとハシブトガラスがいて形態、歩き方、鳴き方の違い、共に夫婦仲がいい。
・アオサギ~川面を優雅に飛行。ツルとサギの飛び方の違い。ツル類は首を伸ばす、サギ類は首をS字に曲げて飛ぶ。
・嘴の形態について解説あり、エサの違い。太い嘴は木の実や種子を食べ、細い嘴は虫などを食べる、スズメは両方を食べる。
・コムクドリ~図鑑P30-オスがきれい、メスは抱卵するので目立たない体色になっている。
・カワラヒワ~嘴は太い。種子を食べる。秋には群れで河原などに100羽単位で見られる。
・コヨシキリ~北海道で見られる。鳴き声きれい。オオヨシキリは本州で多く見られる。
・ここでカッコウの托卵の質問があり、カッコウの托卵成功率は数パーセント程度でカッコウの托卵できる鳥が多くいないと生きていけない。いわばカッコウは環境のバロメーターである。
図鑑の声マークにタッチペンで声を聞かせてくれた。鳴き声を確認できる優れモノ。



・ノビタキ~野にいるヒタキ、北海道に多くいる。15gと軽い。最近分かったことで北海道から一気に群れで日本海を飛び越えて渡り中国を陸伝いに南下し上海付近で越冬。星の位置を見ながら方位観測して渡って行く。この小さな体でビックリですね。
・ノゴマ~観察出来てラッキーです。別名日の丸。北海道だから平原で見られる。本州では高原地帯でしか見られず稀です。歌声は透明感の澄んだ声。

・シジュウカラ
・カワラヒワ~飛ぶと翼に黄色の帯が出て判別できる。
川辺でカモやカモメ類などの水鳥を探すが殆ど見られず。石狩放水路が出来る前(40年以上前)は河口部に湿地が形成されて、長さ200mほどの浅瀬にシギ類が群れていたとのこと。

・ヒバリ~木道の終点周辺の草原はヒバリがとても多くいて、ヒバリ大国でした、縄張りを持っていて、春先は声と姿で自分を盛んにアピールしている。ここは食べ物も豊富でヒバリにとっては高級リゾート地のような所。いい条件とはエサがあること、川のそばは暑すぎずに体温を下げること出来る。巣作りには良い環境でお嫁さんも喜ぶ。
・カモメ~海に向かって飛行する。
質問:雨が降ったらどうするの?メスは巣の中でじっと座って抱卵し続けて卵を守ります。尾の付け根には油脂線があって、体にそこから出る油を全身に塗って水をはじく仕組み。ヒナがいて、近くに(キツネなど)天敵がきたら、親は偽傷(ぎしょう)行動をして、子供たちを敵から遠ざけて守ります。(チドリの仲間)
近づいていくと飛び立つ、有効距離20mを実感しながら移動していく。
石狩を代表する鳥は?にアカモズ、ノゴマをあげる。
・オオジュリン~大きさはスズメ大。よく見られる、歌声も良し、頭は黒頭巾、腹白、湿地の草原やヨシの間に巣造りする。
・ホオアカ~メス、虫くわえていた。子育て中です。
〇東屋で10分休憩
休憩中の話題~北海道のアオサギにはコロニー(集団繁殖地)がたくさんあった。子育て中にアライグマが巣を襲うようになり、コロニーを放棄して、巣場所を求めて放浪の旅をすることになった。今は人が住む住宅街の近くに巣を構えるようになった。アライグマが来ない五ノ戸の森(札幌市北区)緑地にコロニーを作っている。アオサギが出す糞害などで苦情も出ている。
・コヨシキリ~縄張りの範囲は200mから400m四方位。ピンセット型の嘴は昆虫食のため細い。
・ノゴマのさえずりに聞き入る。
鳥の産卵回数について?通常は年1回産卵巣作り。シジュウカラは年2回。
参加者からカモメは獰猛そうだとの意見に対してウミネコやオオセグロカモメの顔つきは荒っぽい印象ですがユリカモメの顔つきは優しそうで可愛いです。

〇ほぼ予定時間でコースを歩きビジターセンターの裏で終了。
・最後に野鳥観察会の案内あり6月第4日曜は石狩浜です。草原では1,2週間で入れ替わる。石狩川河口部ではミサゴの繁殖期行動で川魚をハンティングする様子がよく見られる。
・ビジターセンター2Fのリニューアルの紹介。6月はまなすデイの案内を行った。
〇帰りの車中で今日見られた鳥をチェックシートで確認しました。16種が確認出来ました。
天気に恵まれ期待以上に鳥をまじかに見られたことで参加者の皆さんも満足した観察会でした。
アンケートをいくつか紹介します。
「久しぶりで野鳥のさえずりを聞きました。心が浄化されます」
「ノゴマのさえずりがよかった。ヒバリも大変いそがしそうだった。16種の鳥の生活の一部を勉強できて良かった。反省としては事前に勉強する必要あり」
「フィールドスコープの映像がすばらしく鮮やかでし」
「おだやかで心地よい浜風に吹かれながらの探鳥散策は心に残る講座となりました。講師のお話も楽しいものでしたし、何よりも私自身が閉塞感から開放されて、鳥と共に草原の豊かさを楽しむ時間となりました」
「とても良かったです。なかなか歩くことの出来ない所と鳥のさえずりが心にしみました」
「さわやかな天候の中で貴重な時を過ごせました。解説がないと分からない鳥の名を知ることが出来て良かった」
「色んな野鳥をたくさん見ることが出来た。チゴハヤブサは良かった」
「双眼鏡は持参しなかったが講師が容易に見せてくれた。望遠鏡により10種以上の野鳥が観察できました。この木道には歩くスキーや年に一度位の頻度で訪れるが今日の参加で大河川と海に存在する石狩浜の自然を満喫でき新たな知識を得ることが出来ました」
「さわやかな好天のもと楽しい観察会に参加でき本当に良かった!!和気あいあい時々チェックが入りましたが、人もピーチクパーチクと隣の人との会話も有意義でした。学習しました。これから野鳥の声をきき、姿を見て・・参考になります。感謝!!」
「はまなすの丘公園は良く訪れホオアカ、ノビタキ、ノゴマなどは見てましたが、猿子先生の案内で初めてチゴハヤブサ、コムクドリを見ることが出来ました。大変楽しい観察会でした」








